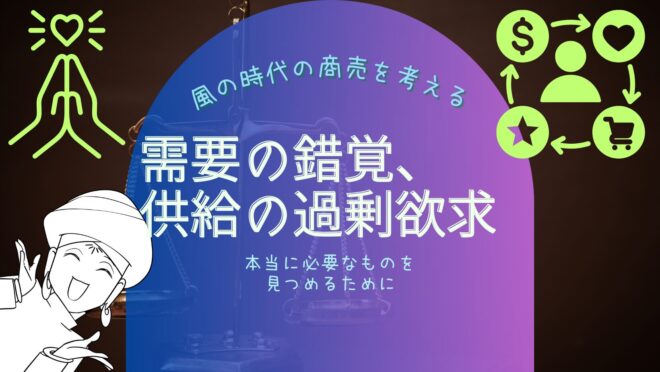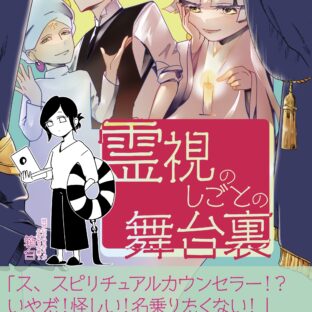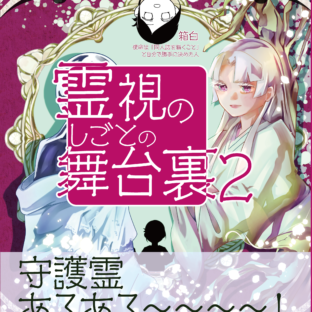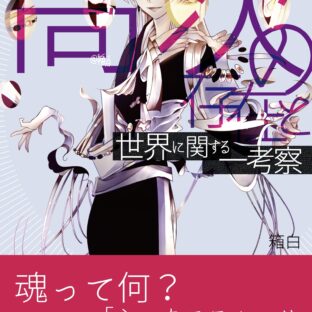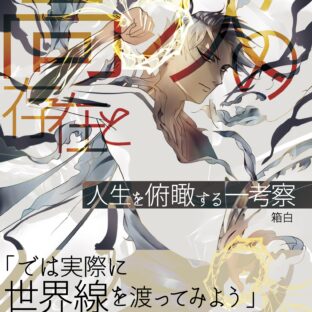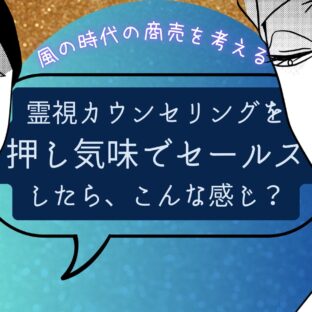生産者の倫理観と現実。需要と供給のバランスが崩れる原因は?
目次
需要と供給のバランス、なんで崩れるの?
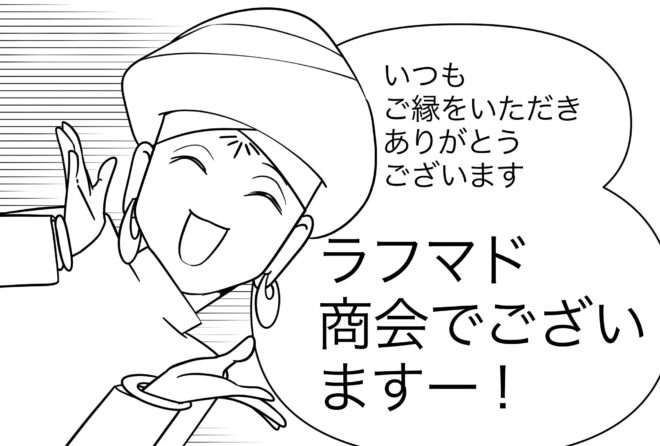
ラフマド「おやあ、私どもをお呼びとは珍しいですねえ」
この記事は、前回の続きです(前回↓)
私「ええ、ここからはラフマドさんに解説頂こうかなって。お商売のことならあなたが詳しそうだし」
ラフマド「私どもの理念は『無限の定理』に基づきます。すなわち、『必要なものに、必要な分だけ、過不足なく、絶対に存在する』。この理念に賛同するものが集まって互いに協力する団体、それがラフマド商会でございます」
ラフマドさん登場回については、以下のブログから見るとわかりやすいかも↓
需要と供給が釣り合わない原因って?
私はラフマド商会さんとは協力関係にあるのですが、そうなるにあたって、ラフマドさんからNGを出された行為がいくつかありました。このNG行為を聞いて、それに賛同したのがラフマドさんと協力するに至った理由の一つでもあります。
ラフマド「需要を錯覚させることは、私どもの理念に反します。よって、そのように意図したマーケティングはお控えくださ……あっ!別にやっても良いですよ?しかしそれをするなら私どもとは相容れないので、一緒にいるのはお互いのためにならないのでさようなら、ということでございます」
そう、先ほどのコピーライティングの話題に繋がるんです、ここで。
ラフマド「本来、需要と供給のバランスは釣り合っているはずの概念です。しかし実際はというと、そこかしこで需要と供給のバランスが崩れ、トラブルが多発しております。それはなぜか?需要の錯覚と、供給の過剰欲求が原因です」
需要の錯覚
「本来自分にとって
必要なものではないが、
外部からの刺激によって
何かが欲しくなること」
これを需要の錯覚と呼んでいるそうです。
ラフマド「前回のブログで、こんな言葉は人の欲求を掻き立てるよ、と考察されていましたね。需要の錯覚を助長する売り方です。私どもはあまり好ましく思っておりません」
夜になんとなくSNSを見てたら広告が流れてきて、絶対にしないと!と急き立てられて、焦りから買ってしまう。もし昼間の落ち着いてる状態で見ても、きっと購入はしなかったのに。
売ってる側は「買ってくれた!やったー!」になるかもだけど、買い手が正常な状態だったら、それは本来はなかった需要。
ラフマド「もちろん、そういう出会い方でも質の良い商品であれば買い手にとって役に立つものである可能性はあります。こういった経緯で買ったものが全て不必要なものだったとは申しません、それは言い過ぎですから」
私「でも、少なくとも本当はそんなに欲しいものじゃなかったのにって思う人の割合は増えると思う」
ラフマド「買い手は本来、まず自分に不足しているものを自覚し、そこから必要なものは何なのかを推測し、過不足なく選択肢を得て、選びながら必要なものに出会ってゆくものなのです。あなたはこうだから必要なのはこれでしょ、と聞かれてもいないのに決めつけてから解決策を与えることは、私どもの理念にはございません」
必要なものがわからない……そういう場合もあるけど、そういうときに手に入れるべきは考える材料。
ラフマド「ただ、売り手側は自分の商品を売るために、考える材料を先に提示してそこから購入してもらえるように導線を引く〜なんて、あるあるです」
自分で考えて選んで買っている……と、買い手は思っている。そのように演出されている。
私「よくあるね。考えさせない売り方は、割と分かりやすく怪しい。でも上手な商売ほど、買い手に考えさせる。考える材料を渡した上で、考えさせるよね」
その考える材料、どこからきた?
極端な例ですが、「この商品50%引きなんですけど、実はセールは今日までなんです。この機会を逃したらもう定価に戻っちゃって、お客様は〇〇円損することになるんです」みたいなセールストーク。
別に今この場で買わないとダメなんて言ってないけど、この場で買わないと損だよとは言っています。
〜ここでの考える材料〜
①商品の定価
②今日限定のセールの存在
③今日買わないと
定価で買わなくちゃいけなくなる
これらがすべて本当のことだったとしてもこの事実を3つ並べるだけで「買った方が得するんじゃない?」って思えてきちゃう不思議。
ラフマド「ええ。仮にそれらが事実だとしても、買い手にとって公平な情報は①と②のみです。③は①と②を組み合わせた売り手の主張です。これが錯覚の原因となります」
これさ、
すごく絶妙な差なの、わかる???
ここなの。これが怪しさが生まれるか否かの差なの。言い換えると、判断材料に売り手の主張が入るか否かなの。
売り手の主張が入ると「買うか?買わないか?」の二択にまで絞れるようになってるの。
ラフマド「もしそこに悪意を見出して言葉にするなら、主張というよりも誘導、でしょうね」
えーーなんかちょっと物騒な感じになってきたじゃん?という暗雲立ち込めてるところで、続いて次の概念です。
供給の過剰欲求
「別に誰かに
求められたわけじゃ
ないけど、自分が
それを売りたい」
これを供給の過剰欲求と呼んでいるそうです。
これも主に売り手の問題。
ある人が「こんな製品を作ったから売りたいな」と思ったとき、その商品を欲しいと思う別の人がいればいいんです。
ラフマド「今の世の中には色々な商品がとても多く溢れていますね。需要に対して供給が間に合っているのです。にも関わらず、さらに供給しようとする人が増えるとどうなりますか?」
私「余る…?」
ラフマド「ええ、余ります。実際、余っています。けれど生産者としてはなるべく余らせたくないものです。あなたも同人誌を作っているなら、わかるでしょう?」
私「うん……たくさん印刷して、でも売れなくて在庫を抱えるのは嫌だね」
本当にいや。まじで。
だからこそ私は、同人誌をするときは最初は予約制にしているんです。余らせることは嫌だし、ラフマドさんに言わせれば「余らせることは罪」だから。生産者は余ってしまったものに対する責任を負うのです。
ラフマド「しかし、予約販売ではない販売方法をとることもありますよね。そして見込みが外れて余ってしまうこともある。そういうとき、生産者はどうしますか?」
私「欲しいと思ってくれる人を探すしかないね」
ラフマド「ええ、そうです。けれどそのためにはかなりの労力と工夫が求められるでしょう。だから多くの生産者は、ここで需要の錯覚を起こそうとしてしまうのです」
生産者の切実な現実
さっきは悪意をもって錯覚を起こすよう「誘導」するなんて表現もチラッと書いたけどさ。でも、生産者側の目線に立つとそれはそれで切実な現実があるんですよね。
一言でいうと、余らせると自分が破綻して生活できなくなるんです。
「これはすごくいいよ!だれか欲しいひといないー?」がいつの間にか「これを買わないと損するよ!」と不安を煽りだす。需要がないのに買わせようとしだす。なぜか?自分が損害を被るわけにはいかない、と思うから。
実際、似たような商品が世の中に多く存在しているこの広い世界の中から、自分の商品を選んでもらう必要がある____それが売り手の事情であり現実です。そしてそれが「そういうものだね」となっているのが、現在の社会。
ラフマド「ただ、これが需要と供給のバランスを崩す原因になります。私どもは、そういった事業者さんとはお付き合い致しかねます」
ラフマド商会さんは事業者や生産者、つまり売り手側の組合。彼らが掲げる『無限の定理」』は「私たちが需要を錯覚させちゃうと、需要と供給のバランスの崩壊を招くので、そういうのやめましょう」という理念でもあるのです。
私「でも…実際余らせちゃうことってあるでしょ、誰も完璧な人なんていないもん。それに、商品が売れないと生活できなくなる人が出る。そういう現実もあるよ?どうすればいいの?」
____実は今、私の隣に同人誌の在庫があります。
いや、ね?一年くらい在庫が残る状態になれば良いなって思って印刷したよ?だから今の時点で在庫がある(余っている)のは別に問題じゃないのはわかってるよ?でもね?気持ちの面でふんわり不安になるのよ?
ラフマド「本当にそれを必要とする人を探し、届けるんです。あくまで現時点のあなたから見える範囲に需要がない、というだけで、自分が見える範囲を広げれば需要があるかもしれませんから」
私「す、すごく当たり前なこと言われてる気がするけど……」
_____しかし実際、この当たり前のことができている事業者がどれだけいるでしょう?むしろこれこそが最大の難関とも言えるのではないでしょうか?
ラフマド「その難関から逃げないでください。正面から向き合い続けてください。需要の錯覚をさせれば簡単に売れますが、易きに流されてはなりません。そして、需要がないと察したなら、それをそのままの状態で売ることに固執せず、需要にあわせて商品をアップデートしていくのです」
『霊視のしごとの舞台裏』エッセイ漫画
商品紹介
「霊視のしごとの舞台裏2」エッセイ漫画同人誌
商品紹介
『高次の存在と世界に関する一考察』ブログ記事まとめ、考察本
商品紹介
『高次の存在と人生を俯瞰する一考察』ブログ記事まとめ、考察本
商品紹介
関連情報